最近、映画を見る前に詳細なネタバレをチェックする人が増えています。映画選びの失敗を防ぎ、時間やお金を無駄にしないためです。
本記事では、そんな方々に向けて『回路』の詳細なあらすじと感想をお届けします。視聴の際の参考にしていただければと思います。また、視聴後に他の人の感想を確認したいときにも役立つ内容となっています。
配信状況
『回路』はU-NEXTで現在見放題配信中です。TSUTAYA DISCASの宅配レンタルもオススメです。
U-NEXTは国内最大級の見放題作品数を誇り、映画のラインナップも業界トップクラスです。初回登録なら31日間の無料体験ができて、さらに600円分のポイントがもらえるので、新作映画や有料作品にも使えます。
この機会にぜひチェックしてみてください。
\31日間無料で試す /
映画情報
あらすじ
あらすじを動画で見る(おすすめ!)
あらすじをテキストで読む
舞台は西暦2000年頃、インターネット黎明期。観葉植物の販売店で働く工藤ミチの同僚・田口が、1週間も無断欠勤して行方がわからなくなってしまったんだ。心配になったミチは田口の自宅を訪ねてみるの。すると田口は何事もなかったかのように普通にそこにいたんだ。安心したのも束の間、ミチが少し目を離した隙に、田口は首を吊って自殺しちゃったんだよ。さらに田口のパソコンには、田口自身が写っている奇妙な画像が残されていたんだ。一方その頃、大学生の川島亮介は、自分のパソコンが勝手に見知らぬサイトに接続される現象に悩まされていたの。画面にはどこか知らない人の姿が映し出されて、「幽霊に会いたいですか?」なんて文字が出てくる。パソコンに疎い亮介は困って、パソコンに詳しい理工学部の唐沢春江に相談することにした。知的で美人で愛想もいい春江はこの怪現象に強い興味を示し、幽霊サイトの調査に協力してくれることになったんだよ。
ミチの同僚である矢部にも不可解な出来事が起きるの。彼の携帯に突然「タスケテ…」という謎の電話がかかってきたんだ。不審に思った矢部は引き寄せられるように田口の部屋へ向かってしまうんだ。部屋には「あかずの間の作り方」と書かれた紙が残されていて、矢部は奥の部屋に足を踏み入れたの。壁には田口が首を吊った場所に大きな黒いシミができていて、まるで田口自身がシミになっちゃったみたいでゾッとするよね。その後、矢部は赤いテープで封印された部屋に迷い込み、そこで何か得体の知れないものに遭遇してしまう。この出来事を境に、矢部はまるで別人のようになってしまったんだ。その後、ミチの勤める会社の社長も忽然と姿を消してしまう。そして矢部も最後には「タスケテ…」という言葉を残して壁の黒いシミになって消えてしまったんだよ。極めつけには、ミチの一番の親友だった同僚・順子までが赤いテープの“あかずの間”に入ってしまってね。順子は茫然自失の状態になってしまい、やがて塵のようになって消えてしまったの。こうして次々と仲間が消えていき、気づけばミチの周りには誰もいなくなってしまったんだ。
一方、亮介の周りには黒い人影のような不気味な存在が出没するようになっていた。捕まえようとして追いかけても、それはスッと消えてしまうの。そんな様子を目撃していたのが、春江の研究室の先輩・吉崎。彼は幽霊について独自の仮説を語り始めるの。「あの世で受け入れられる魂の数には限界があって、溢れた魂はこの世に来るしかない。そして何らかの儀式で呼び出された魂は、インターネット回線を通じて世界中に広がってしまった」――つまり赤いテープで封印された“あかずの間”は、幽霊をこの世に召喚するための装置だったってわけ。呼び出された幽霊たちは、人間の魂があの世に行かないように、この世で人間を黒いシミに変えてしまっていたんだ。幽霊は瞬く間に世界中に拡散して、街からは人の姿が消えていく。そんな異常事態の中、知的で冷静だった春江も幽霊の存在に心を奪われてしまったみたいで、次第に様子がおかしくなっていくんだ。亮介は春江と一緒に遠くへ逃げようとするけど、春江は亮介を拒み、ついには姿をくらましてしまった。
そして閑散とした街の中で、ついにミチと亮介が巡り会うんだ。一度は春江の捜索を諦めていた亮介だけど、ミチに励まされて二人で春江を探し続けることにしたの。そうしてようやく廃工場で春江を発見したんだ。だけど、現実に絶望してしまっていた春江は、二人の目の前で自ら命を絶ってしまう…。亮介は工場でガソリンを探していたんだけど、そこで春江が作った“あかずの間”を見つけてしまい、幽霊に遭遇しちゃうんだ。亮介は金縛りにあったように体が動かなくなるんだけど、ミチがなんとか彼を支えてその場を逃れたよ。二人はもう二度と振り返らず、できるだけ遠くを目指して走り続けた。車で逃げに逃げてガソリンが尽き、最後はモーターボートで海に漕ぎ出す。幸い通りがかった船に保護された二人だったけど、その船にも生存者は僅かだったの。世界中でも人々が消え続けていて、生き残りを探す航海をしているところだったんだ。やっと安全な船に逃げ延びたかに見えたミチと亮介だけど…船室の壁には、いつの間にか亮介だったはずの黒いシミが残されていたんだ。
『回路』は、インターネットを介して幽霊が世界に拡散するという異色のホラー。派手に幽霊が出てきたりグロテスクなシーンはないんだけど、その代わり底知れない孤独感と世界の終わりみたいな絶望がじわじわ迫ってくるんだ。誰もが繋がれるはずのネットが、逆に孤独を増幅させるっていう皮肉な怖さが際立ってるよね。ネットが今ほど普及していないから作ることのできた、時代が生んだ名作だと思うよ。
感想
『回路』は、インターネット黎明期ならではの“未知”への不気味さとホラーを融合させた異色作だよね。公開当時、日本のインターネット普及率はまだまだ低くてパソコンやネットが今ほど身近じゃなかったからこそ、電源を入れた先に広がる謎のサイバー空間に「もしかして何か恐ろしいものが潜んでるんじゃ…?」なんて漠然と不安を感じた人も多かったと思うんだ。『回路』はまさに、そんな時代の空気をすくい取って「インターネットから幽霊が滲み出す」という奇抜な発想でゾッとさせてくれる作品だよね。
人を繋げるはずのインターネットで逆に孤独が浮き彫りになるって構造が面白いんだよね。2001年当時にそこに気づいて、ホラーに絡めて描いてた黒沢監督の鋭さには改めて驚かされる。SNSとかが普及した今でこそ、「ネットで繋がってるのに孤独」って問題がリアルに感じられるけど、あの時代、まだネットに繋ぐときって「未知の世界に入る」感じが強かったし、「世界中と繋がれるのに、なぜか孤独感が深まる」っていう皮肉な構造が秀逸。
ちょっと内容は違うけど、昔見た、シリアルエクスペリメンツレインってアニメに似てるんだよね。あれも『回路』と同じで、インターネット黎明期に作られた作品で「ネット空間と現実世界が曖昧になっていく不安感」とか「ネットが広がるほど孤独になる人間」みたいなテーマが描かれてたよね。レインの場合は、ネットと現実が融合して人の意識がネットの中で混ざり合っていく、みたいなサイバーパンク的な世界観なんだけど、『回路』の「幽霊がネットを介して現実に侵食してくる」ってのも、すごく近いものを感じる。どちらもネットの拡張によって生まれる「繋がりの不安」とか「自己の消失」とかを描いていて、ちょっと難解だけど強烈に心を掴まれる感覚が似てるよね。『回路』が好きなら、きっと『レイン』も響くし、その逆もまたしかりって感じ。
同じ黒沢監督の『CURE』とも通じる部分があるよね。『CURE』も『回路』も、直接的に何かに襲われるってよりは、もともと人間が持ってる心の闇や孤独みたいな「内側の弱さ」を外的なきっかけ(催眠や幽霊)で引き出されてしまう感じだよね。『CURE』の場合は、催眠によって抑え込んでいた怒りとか憎悪のストッパーが外れてしまう。それってつまり「犯人」は実は元から自分の中にいるわけで、催眠が引き金になっただけなんだよね。それと同じで『回路』も、幽霊が直接的に殺すんじゃなくて、幽霊が介入することで、人が普段は抑えている「孤独感」が爆発的に増幅されてしまう。
ミチと春江がすごい対照的っていうか、春江はそれが顕著なんだよね。春江が幽霊の存在に気が付いた時、表情にどこかホッとしたような、穏やかなものが混じっているように見えるんだよね。それってつまり、彼女にとっては幽霊に取り込まれること自体が一種の「救い」になってしまっているのかもしれないってことだと思う。もちろん、それが本当の意味での救済とは言えないけど、「孤独でどうしようもない人生」よりは、マシだったのかもしれない。悲しいけど、どこかで「救われた」とも受け取れてしまう。だからこそ観ている側としても、単純な恐怖とは違う、すごく複雑な気持ちになるんだよね。黒沢監督は、こういう「恐怖の中の救済」みたいな曖昧で複雑な部分を描くのが抜群にうまいと思う。「怖いけど、どこか救われている」という、この複雑な後味が黒沢作品を特別なものにしてるんだろうなぁって改めて感じる。
『回路』の幽霊たちってめちゃくちゃ地味なんだよね。ハリウッドホラーに出てくるようなグロテスクな怪物でもないし、「バーン!」と驚かせてくるような音響演出もほとんどない。それなのに存在自体が異様で怖いんだから本当にタチが悪いよね。違和感の塊みたいな気持ち悪さがあるんだ。画面の端にひっそり立ってたり、背後にいつの間にか現れてじっと見つめてきたり…幽霊の方から「わっ!」と派手に襲ってくるわけじゃないのに、気付くとそこにいる。この「いつの間にかすぐそばにいるかもしれない」っていう静かなのに嫌~な恐怖が、心にズシンと響くんだよなぁ。黒沢監督は音や光でビックリさせる代わりに、静寂と空間の不気味さで攻めてくるから、怖さの質が独特なんだ。何も起こらない“間”の取り方もうますぎて、登場人物と同じ空間に自分もいるような感覚になる。気づけば最初から最後までずーーっと不穏な空気に包まれてるのに、それでも目が離せないんだから本当に恐ろしい魅力だよ。
この映画、普通に考えると「え、これどういうこと?」って部分が山ほどある。でもさ、不思議とそれが嫌じゃないどころか、逆にクセになる魅力になってるよね。分からないってことはつまり「答えがない」ってことで、観た人それぞれが自由に解釈できるってことだと思う。だからこそ、何度観ても新しい発見があったり、前は全然ピンとこなかったシーンが突然心に響いたりするのかも。映画って必ずしも全部理解できなくてもよくて、むしろ意味不明な部分があるからこそ観終わった後にずっと頭の中でグルグル考えちゃったりするよね。その感覚が気持ちよかったりするのが映画の面白いところだと思うんだよね。
特に印象的なのがテレビで消えた人たちが淡々と読み上げられるシーン。あれも全然意味わかんないし、冷静に考えると「誰が放送してんの?」ってツッコミたくなるけど、不思議と心に刺さるんだよね。あのシーンって、たぶん理屈で言うと「幽霊たちが放送を支配してる」的なことになるんだろうけど、正直そんな説明なくても全然よくて、むしろ何の説明もないからこそ不気味さが際立ってるよね。淡々と読み上げられる無機質な声だけで、世界が静かに終わっていく感じがリアルに伝わってくる。
『回路』って作品は、まさにそういう「よく分からないけどなんか好き」な演出の宝庫なんだよね。意味なんて後付けでいいから、あの独特の雰囲気だけを浴び続けていたい、みたいな。黒沢監督がやると、ああいう無意味なシーンすら特別な味わいを持つから不思議だよね。
全体的に説明不足で謎だらけなんだけど、それが逆に未知の恐怖を際立たせているとも言えると思う。丁寧に全部説明されちゃったら、この不気味さは出なかっただろうなぁ。観終わった後も「結局どういうことだったんだろ?」ってモヤモヤ考え続けちゃって、頭から離れない感じ。じわじわ効いてくる余韻が凄まじくて、観客を孤独の恐怖に取り憑かせるような一本だと思ったよ。ホラーとしてもSFとしても異色だけど、個人的にはかなりお気に入りの作品だね。


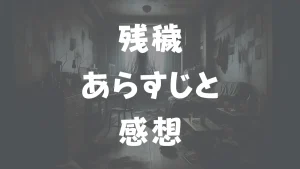
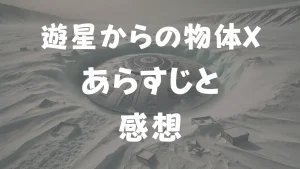
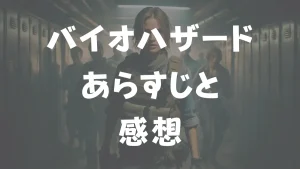
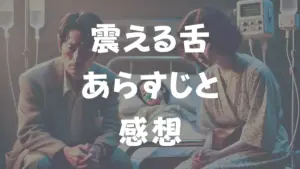
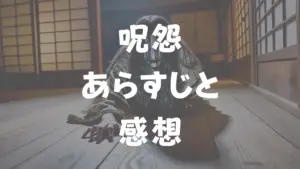
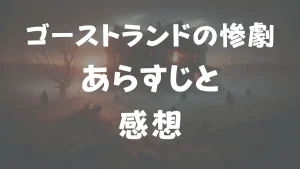
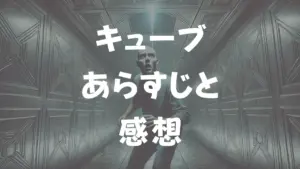
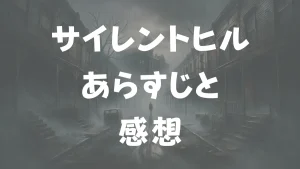
コメント